授業、サークル、バイト……。クラスごとに時間割が決まっている高校生とは違い、大学生は時間の過ごし方の多くを自分で決めなければならない。また、それ故に自分の選んだ道が自分の学びや成長の方向性、楽しみ方を大きく左右することになる。そんな大学生活で、社会課題の「解決」に本気で取り組むのはどうだろう? 東大が誇る「学生シンクタンク」瀧本ゼミ政策分析パートの豊井美雪さん(理Ⅱ・1年)、堀江健太郎さん(法・3年)に、同ゼミの活動について話を聞いた。
(取材・中野快紀)
構造的な解決に踏み込め
──瀧本ゼミ政策分析パートがどんな団体なのか教えてください
豊井 社会課題の解決を目指す学生シンクタンクだと考えていただければと思います。主に政策立案をして、それを自治体などに提言する形で活動しています。しかし、その方法でないと駄目というわけではありません。過去にはゼミで調べた内容を基に論文を書いたゼミ生もおり、各自の自由な発想で活動しています。
──ゼミに入った経緯を教えてください
堀江 元々社会課題に関心があったのですが、社会課題を扱う学内の団体の中でも瀧本ゼミには実際に社会課題を解決した実績があること、そして「構造的に解決する」ことを志向している点に引かれ、入ることを決めました。構造的に解決する、ということはどういうことかといいますと、例えば「水の足りない村に水を送るにはどうすれば良いか」を考えるとしましょう。その際、自分が毎回井戸まで水をくみにいく、というということが考えられるかもしれません。それも確かに重要なことです。ただ、それだけでは構造的な解決になっているとは言い難い気がしています。そのため、例えば水路を通すなど、問題の構造から変えることが必要になります。自分が水をくみにいくような草の根の活動ももちろん重要なのですが、瀧本ゼミでは問題をもう少し俯瞰(ふかん)して、中長期的に役に立つ課題解決をしていこうとする考え方をしています。自分自身に与えられた限られた時間とリソースで社会課題を解決しようとするならば、構造的に取り組んだ方が良いと思い瀧本ゼミを選びました。
──ゼミでの活動を通じてご自身に変化はありましたか
堀江 「分かりやすい選択肢」を選ばなくなったと思います。構造的にものを見る癖が付いたことで、日々の選択の際に、なんとなく良さそうで、流行っているものを思考停止で選ぶことがなくなりました。人から与えられた情報を鵜呑みにせず、自分の頭で考えて結論を出すという瀧本ゼミでの経験は大きかったです。

行政と連携し、解決につなげる
──2021年度にゼミで取り組んだという、「中央区における認知症予防策」について教えてください
豊井 人が認知症になるまでの状態の一つに「MCI(軽度認知障害)」があります。MCIの状態を過ぎると認知症となり、一度認知症になってしまうと治ることはありません。そこで、MCIの状態の方を見つけることで、認知症を予防できないかと考えました。その内容をまとめて昨年の11月に東京都中央区の議員の方に提言したところ、議会でも取り上げていただき、現在区内の聖路加国際病院との連携などを検討していただいています。
──問題意識を持ってから提言にまとめるまでの流れを教えてください
豊井 認知症予防の提言については家族が認知症になった経験もあり、認知症の進行の速さについての問題意識から始まりました。最初は「運転免許の更新が3年単位だと認知症の進行に間に合わないのではないか」という仮説を立て、リサーチを進めていきました。その中で仮説が正しそうだと分かってきたのですが、一方で運転免許をただ取り上げても駄目だということに気が付きました。
そこで、認知症そのものを予防していく方向にシフトし、改めて徹底的に文献を調べたり自治体にヒアリングを行ったりして、仮説を裏付けていく作業を行いました。さらに施策の実現可能性や効果についても調べ、最終的に提言にまとめました。
重要なのは「何をやるか」より「誰とやるか」
──ゼミに入るにはどうすれば良いのでしょうか
豊井 志望する方には、4月中旬から下旬にエントリーシートを出していただきます。エントリーシートの項目は志望動機と自分の興味のある社会課題、自分なりの解決策の三つです。その後に約30分の面談を行い、新入生の皆様の関心を知りたいなと思います。
──瀧本ゼミとしてはどのような人を歓迎したいですか
豊井 瀧本ゼミを志望する方に持っていてほしいものは、第一に粘り強さです。社会課題の解決策を考えたり、政策立案をしたりするのは難しい作業で、うまくいかないことの方が多いです。そのため、粘り強さを持っているゼミ生が成果を出しているように感じています。
また「こういう人だとゼミを楽しんでくれそう」という観点だと三つの人物像があります。まずは社会課題に関心がある人。本当に解決したい問題がある、自己満足は嫌だ、という人にはおすすめです。次に研究者気質、好奇心が強いという人です。ニッチな分野のリサーチにも喜びを見出せるタイプの人にも合っているのかなと思います。そして最後は東大に入ってとにかく成長したいという人。難しい課題を解決していく中でさまざまなスキルを身につけることができます。
堀江 ゼミに入るにあたって特別なスキルは必要ではなく、大事なのはマインドだ、というのが私の見解です。大学生は高校までと比べて成長の速度が速いですし、成長には個人差もあるので、スキルはこのゼミで学んでいただければ大丈夫です。大事なのはマインドで、議論を楽しめる人、課題解決に対してエネルギーがある人が向いているかと思います。
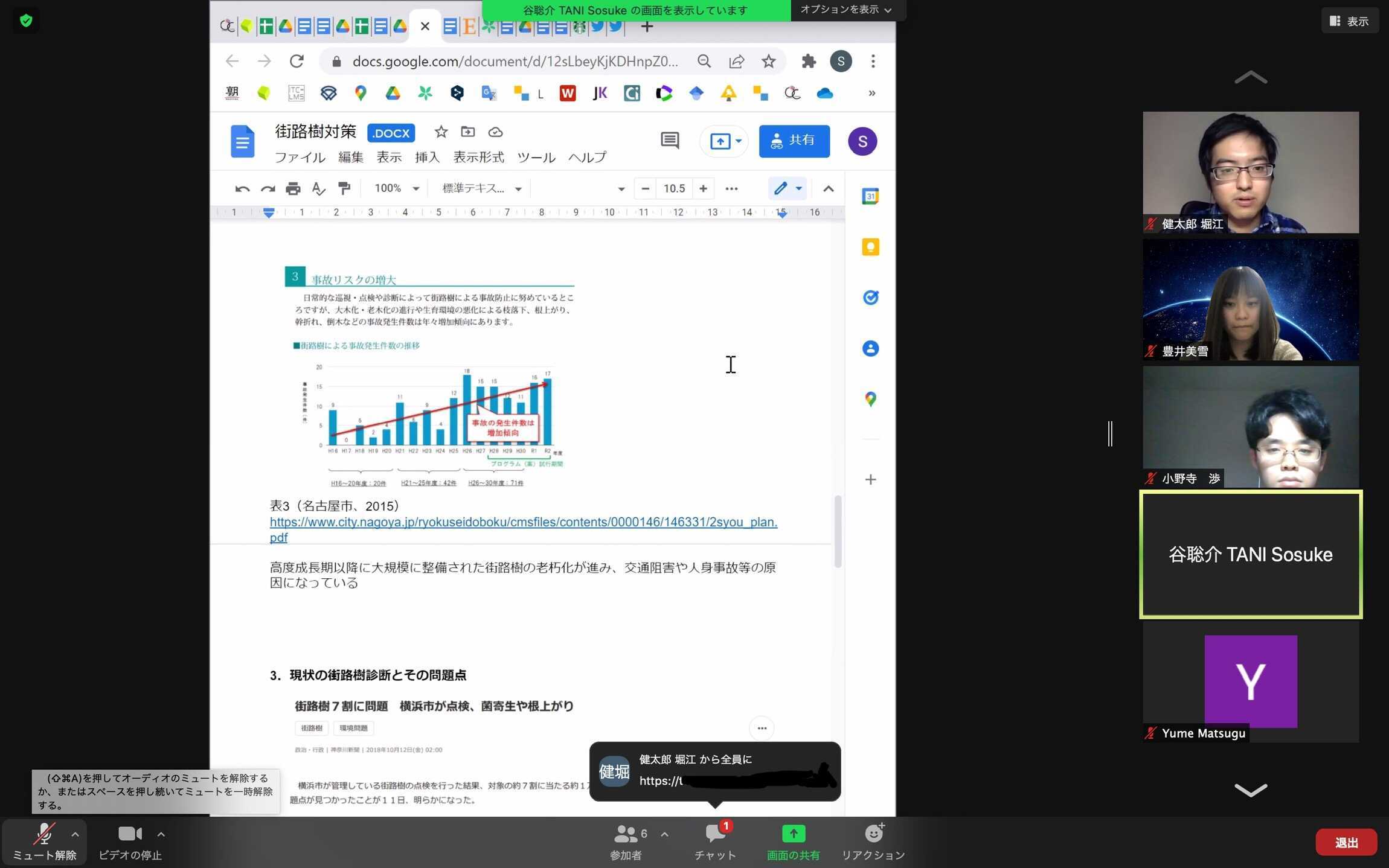
──最後に、ゼミに興味を持っている新入生にメッセージをお願いします
豊井 興味を持ってくださっている方にお伝えしたいのは「瀧本ゼミ政策分析パートは学生シンクタンクとして日本トップレベルだ」ということです。他の団体と迷っている方もいるかもしれませんが、入る前には予想もしていなかったことを得られるのがこのゼミです。クオリティが高く、現実可能性の高い政策を作ることを求め合う空気は他の団体にはないと思います。
新歓情報
【新歓イベント】
3/27 午後9時半〜 UT-BASEの合同新歓に参加(22:11から説明予定。前後する場合もあり)
4/10 午後7時〜 東京大学新聞社、東京瀧本ゼミ企業分析パートとの合同新歓
4/13 午後7時半〜 「行政の先取りも?! 瀧本ゼミの政策立案」
4/16 午後2時〜 「はじめての政策立案!ゼミ生と一緒にやってみよう!」(実践ワークショップ形式で行うため、人数を制限する場合もあり)
4/18 午後7時半〜 「実績多数!瀧本ゼミのロビイング」
【選考】
4月上旬 TwitterなどでESのフォームを公開
4/25 ES締め切り。提出した方から順次面談
最新の情報は瀧本ゼミ政策分析パート公式Twitter@tsemiseisakuから。
【記事修正】2022年3月30日午後8時17分 サムネイルを差し替えました。
The post 東大発「学生シンクタンク」の正体は? 瀧本ゼミ政策分析パートインタビュー first appeared on 東大新聞オンライン.
