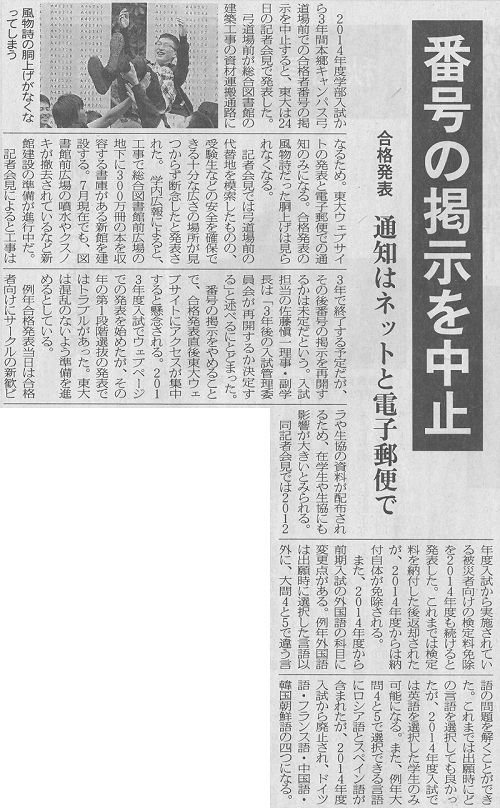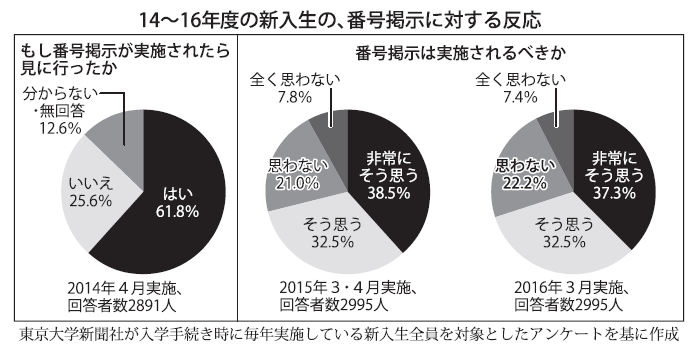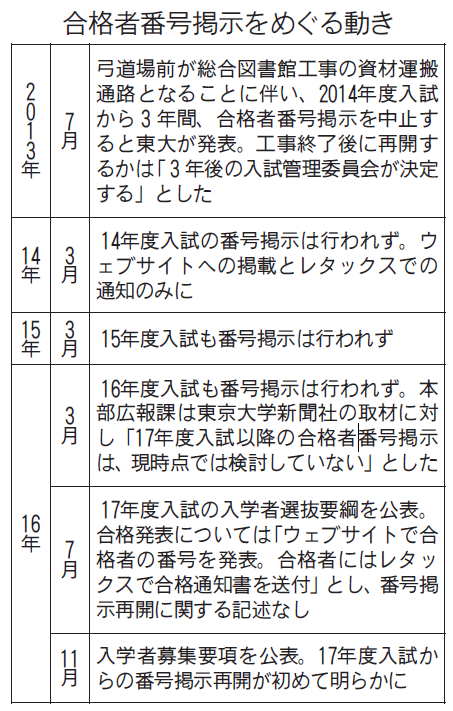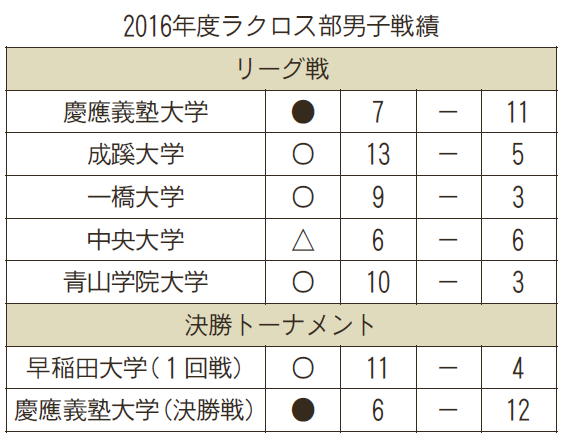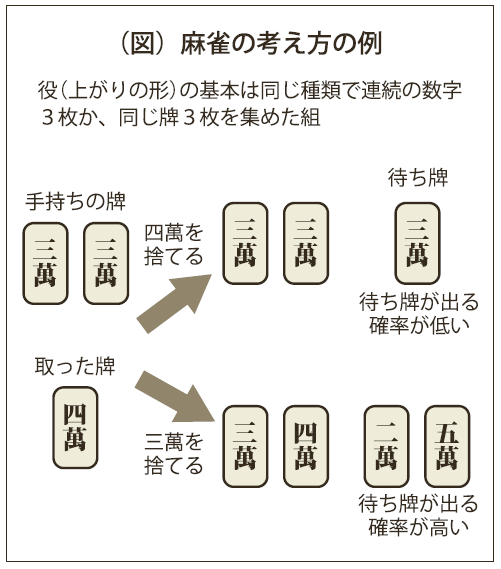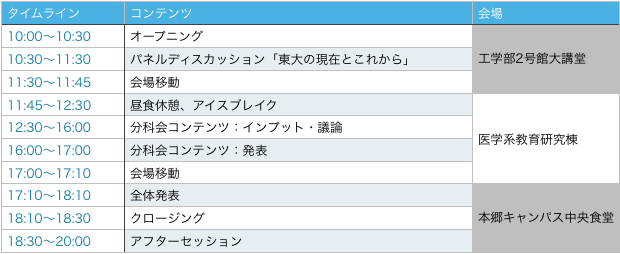入学直後の学部生が1年間の休学を申請し、自主的な社会活動を行う制度「FLY Program」。2017年度入学生で5年目を迎えるこの制度だが、具体的な内容を想像しにくいと感じる人は多い。今回はFLY Program経験者2人に1年間の活動内容を聞くとともに、FLY Program推進委員長の中村尚教授(先端研)への取材から、その沿革と今後の方針を探る。(取材・竹田椋太)
戦争体験者を訪問 横字史年さん(文Ⅲ・1年)
終戦70周年を迎えた2015年、横字さんは「あの戦争は何だったのか」をテーマに、FLY Programを実行した。横字さんを突き動かしたのは「自分たちが戦争体験者の声を直接聞くことのできる最後の世代であることへの使命感」。「なぜあえて1年遅れるのか」という周囲の反対は、かえって横字さんに「成果を出し、周囲に見せつけてやろう」と思わせたという。
横字さんは、1年間を通じて、かつての戦地への訪問や戦争体験者へのインタビューを行った。中でも、木更津海軍航空隊の特攻隊員だった人の話しぶりは、横字さんの脳裏に焼き付いた。凄惨(せいさん)な戦争の中で青春時代を過ごした話から、戦争の背後には「自らの人生に意義を見いだそうと熱く燃える、生身の人間の姿」があることに横字さんは気付く。「書類や映像に見る無機質な戦争には現れない、人々が持つ戦争観そのものを理解することが重要だと意識するようになりました」
![]() 元海軍航空隊特攻隊員に取材する横字さん(右)(写真は横字さん提供)
元海軍航空隊特攻隊員に取材する横字さん(右)(写真は横字さん提供)
活動を海外に広げる中で、横字さんは戦争に対する考え方をさらに深めていく。インドネシアでは、第2次世界大戦時の日本軍の占領以上に、その後の内戦こそが悲劇だったという意見が多かったこと。また、ベトナム戦争やイラク戦争の傷が深いアメリカでは、真珠湾は「観光地」と化し、式典で未来志向の日米関係が強調されていたこと。これらは「国民が共有する『語り継ぐべき戦争』が、歴史・政治体制・文化の違う国同士では異なる」ことを意味する。それぞれの国の立場から戦争を考え、対話を重ねる中で「人の意見を咀嚼(そしゃく)し、反論する力や自信が付きました。学問に対する甘さが引き締まった気がします」。
一見すると回り道のようにも思えるFLY Program。しかし「深く自分の人生を考える契機になった」と横字さんは振り返る。「自分と対話して、何がしたいのか答えが出ない人にこそ、この制度は向いていると思います。自分自身が思ってもみないような人間に成長して、結果的には目標への到達は格段に速くなるのではないでしょうか」
被災地で学習支援 中村彬裕さん(文Ⅰ・2年)
中村さんがFLY Programを知ったのは、高校2年生の時。「自分で計画を立て1年間自由に過ごせるFLY Programは、その頃から視野に入れていました」。参加を決めた当初、中村さんは海外への留学を考えていたが、合格発表翌日の3月11日に「震災から3年」を特集する新聞記事を読み、東北での活動を決意。決め手は「あれほど大きな震災があったのに、自分がその現状をほとんど知らないことに対して持った」強い問題意識だった。
中村さんは、最初の半年を宮城県気仙沼市で、残りの半年を岩手県大槌町(おおつちちょう)で過ごし、学習支援を通じたインターン活動を行った。被災地での体験は「首都圏の進学校に通って東大に入学し、自分と同じような価値観を持っている人との関わりが多かった」中村さんに衝撃を与えた。中でも印象に残っているのは、自転車が壊れてしまった子の「どうせ支援費で新しいのが買える」という発言。支援を受けることが日常化した環境だからこそ出る一言を、責めることはできない。中村さんは、いまだにこの出来事をどう解釈すべきか分からないという。
後半の半年を過ごした大槌町は、震災の津波で線路が流されてしまった町だった。遠方への通学ができない学生の教育の機会は制限され、中学生の勉強への意欲も減退していた。そんな逆境の中でも「勉強が苦手で学校の勉強についていけない中学生が『中村さんの所属する学習施設でなら、高校受験に向けて頑張れる』と話し、真剣な目で勉強をしていました」。英語の学習指導を通じて子どもたちの助けとなれたことに、中村さんは活動の意義を感じたと話す。
![]() 「気仙沼みなとまつり」で、地元の中高生と「はまらいんや踊り」を踊る中村さん(左)(写真は中村さん提供)
「気仙沼みなとまつり」で、地元の中高生と「はまらいんや踊り」を踊る中村さん(左)(写真は中村さん提供)
こうした学習支援活動を通して持った教育への興味から、中村さんは教育学部への進学を決めた。FLY Programの1年で、その後の進路が明確になったという中村さん。「まずは自分がやりたいと思えることを見つけるのが大事。休学をするかしないかという形式的なことではなく、自分自身が1年間の中で何を得たかということが重要だと感じています」
推進委員長・中村尚教授(先端研)
FLY Programの原点は、濱田純一前総長の「よりタフに国内外で活躍できる学生に育ってほしい」という考えにあると語る中村教授。「欧米で主流な、入学を1年間遅らせる制度『ギャップイヤー』の理念を取り入れようと、4カ月の準備期間で作りました」
1年目の2013年度は「突貫工事」だったが、日本では類を見ないこの取り組みは、当初からマスメディアや経済界の注目を集めた。さまざまな企業や非営利団体が後援し活動を支える体制が構築されたという。「理念を支持する企業が多いことの表れです」
中村教授によると、FLY Programの理念は大きく分けて四つある。「一つ目は自主性。海外の留学制度にただ乗るというのでは駄目。何かを組み合わせて、独自性を出す必要があります。二つ目は長期性。一年間休学する価値のある活動をしてほしい。三つ目は社会性・国際性。国内外のさまざまな価値観に触れ『受験勉強マインド』を相対化し、大学に入った後の学びへ生かしてほしい。四つ目は公共性・規範性。ルールの中で自主性を発揮しながら、他の学生の模範となる活動が望ましい」
試行錯誤を経たFLY Programは現在、制度の充実を目指して組織固めをしている。「より多くの部局に担当教員を選出いただくようになってきました。安定した制度となった今だからこそ、ウェブサイトやオープンキャンパスを通じて中学生や高校生への認知度を上げていきたい」。中村教授によるとFLY Programは発展途上。「1期生はまだ3年生。卒業して社会で活躍するFLY修了生に惹(ひ)かれて参加する学生が出るような『循環』ができた時、初めて制度が完成すると考えています」
中村教授から参加を考えている学生へのメッセージ
FLY Programの本締め切りは4月の初旬ですから、参加は東大に入学する前から考えてほしいんです。合格したらFLY Programという制度をぜひ視野に入れてほしい。大学の支援の下、4年間で何を学ぶのかという動機付けを1年間かけて行える、またとない機会ですから。
FLY Programに参加して卒業が1年遅れることをリスクと考える向きももちろんあります。しかし、その1年は他の学生が持ち得ないかけがえのない1年です。その後の人生における自主性が格段に備わり、ハンデを大きく凌駕する実りが必ず得られるでしょう。ぜひ、早いうちから計画を立てて、FLY Programに臨んでください。
【東大受験生応援連載】
2次試験の次は入学準備を 東大生協が入学準備説明会を開催
合格後のスケジュール 計画的に入学準備を進めよう
第二外国語を決めよう!履修者から見た中国語の姿
第二外国語を決めよう!履修者から見たイタリア語の姿
第二外国語を決めよう!履修者から見たフランス語の姿
第二外国語を決めよう!履修者から見たロシア語の姿
第二外国語を決めよう!履修者から見たドイツ語の姿
第二外国語を決めよう!履修者から見た韓国朝鮮語の姿
【東大受験生応援連載】入学直後に東大を飛び出す「FLY Program」とはは東大新聞オンラインで公開された投稿です。