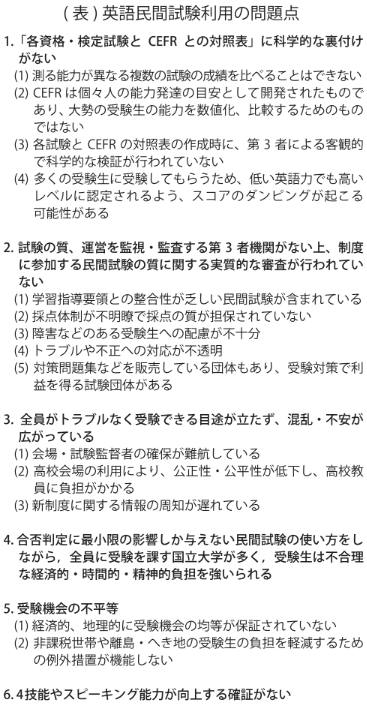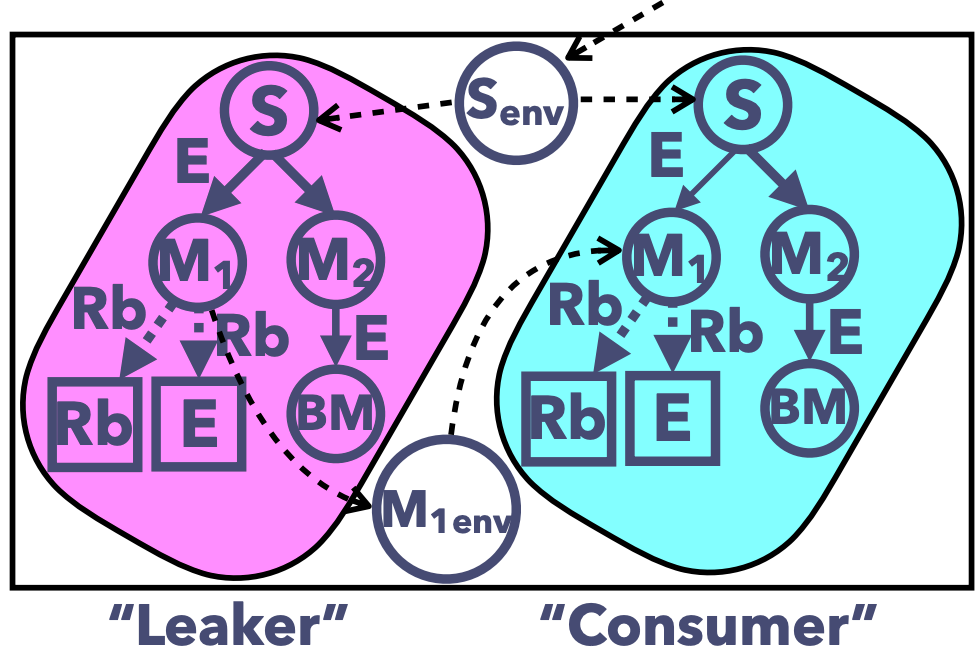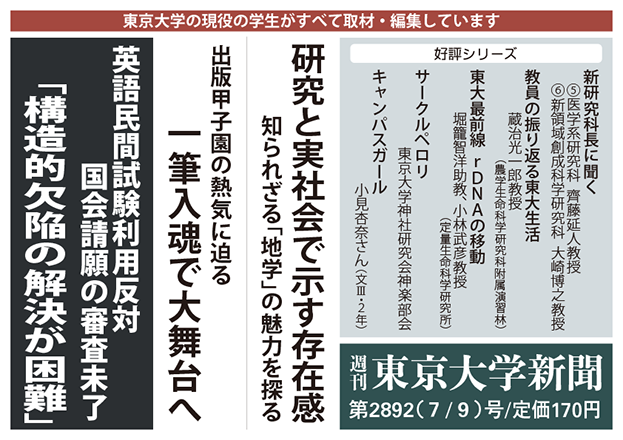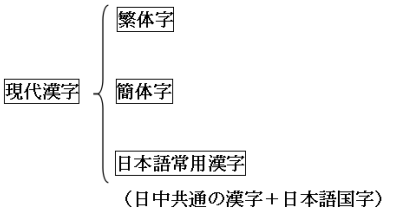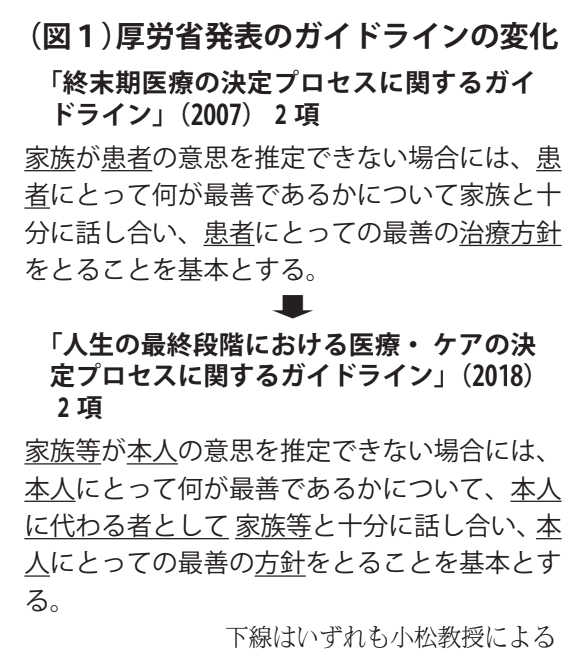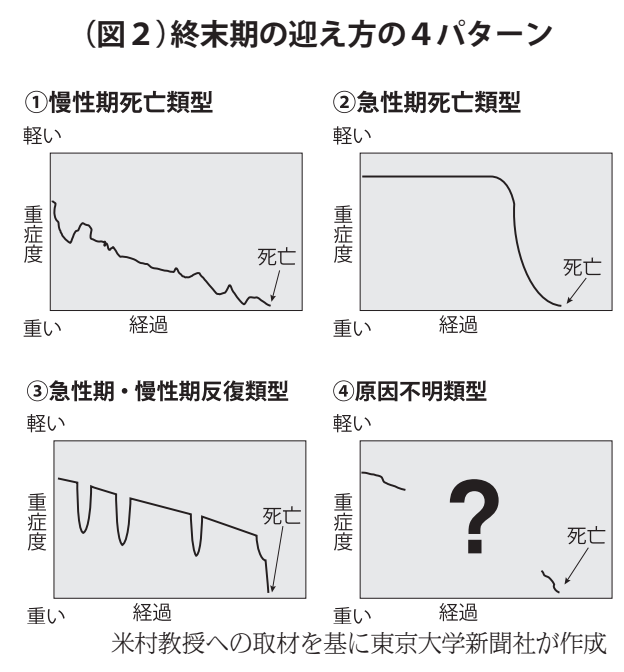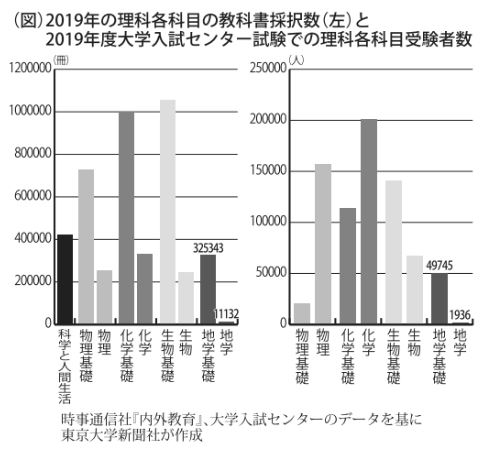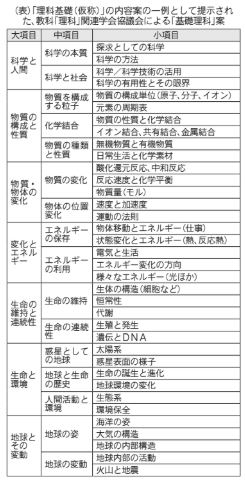近頃何かと話題のふるさと納税。
そんなふるさと納税で全国9位、約39億円(平成29年度)もの寄付を集めた自治体がある。人口約3000人の小さな町 奈半利(なはり)だ(東大の新入生は1年間に約3000人、奈半利は全世代で同じ規模なのだからその規模感はなんとなくイメージできるだろうか)。
税収が2億円ほどの町に、突然40億円近い寄付がやってきた。ふるさと納税の光と影、小さな町の今をお伝えする。
奈半利へ!
「あなないなすびさんの穴内です」(電車のアナウンス)
「ん!?」電車でうとうとしていた僕は謎のアナウンスにびっくりして目が覚めた。「なんだなんだ??(笑)」
「あなないなすびさん」は穴内駅のご当地キャラ。どうやら、アンパンマンの生みの親、やなせたかしさんの仕業らしい。土佐くろしお鉄道ごめん・なはり線では各駅にこうしたご当地キャラがいる。高知県はやなせたかしさんの出身地、高知駅でアンパンマンが至るところにいたのを思い出した。
「なはりこちゃんの奈半利です」
高知駅からおよそ80分、奈半利町に到着だ。

今回の旅で共に回ることになっている川本亮(医学部3年、Grubin代表)、東加奈子(経済学部3年、2か月前に食堂でたまたま知り合い意気投合した)とは奈半利で合流することになっていたが、数時間早く着いたため、お昼ご飯を求め1人奈半利の街を歩くことにした。

奈半利のママ
奈半利の街を歩くがなかなかお店が見つからない。歩き疲れた末に、昔ながらの喫茶店に入った。店内は一昔前の雰囲気。どこか懐かしい。
そこで、お昼を頂いて一息ついていたが、お店のお母さんと話すこともなく静かな時間が流れた。こちらから声を掛けないと、気まずい沈黙……というよくあるパターンだ。
せっかくなので、思い切って声をかけてみた。
「お母さん、このお店はいつからはじめたの?」

お母さんは奈半利の街で初めての喫茶店を50年前にオープン。昔はたくさん取材が来たんだとか(それくらい喫茶店が珍しかったらしい)。夜には2階のスナックを切り盛りするなど、「奈半利のママ」的存在だ。
ここ奈半利は、かつてカツオ船が水揚げをして大いに繁盛していたそうだ。しかし、今は静岡の方で水揚げをするようになってしまったのだという。そして、一昔前はダムの建設に従事する人達でにぎわっていたが、ダムの完成と共に一気ににぎわいは去って行ってしまった。
「奈半利は特産品とかってあるの?」と聞いてみたが、「あんまりない」のだと言う。
お母さんと話をしていると、常連のお父さんがやってきた。

お父さんは50でサラリーマンを辞めて、なすびを作り始めたという。有名なものはあまりないとのことだったが、奈半利も含めた一帯は”なすび”が有名なのだそう(ただ、観光などで推せるほど有名ではないのも確かだ。”有名”というよりは”特産”といった方が正しいかもしれない)。電車の窓からハウスがたくさん見えていたが、きっとそのうちの一つなのだろう。
そうしてお父さんのなすび作りの話を聞いていると、なんと、お父さんのなすび園、息子さんが継いでくれるのだそう。
「こんなの継いでもいいことないのにな(笑)」
そんなこと言うけどお父さん、今すっごい嬉しそうな顔してるやん!
奈半利町役場へ
奈半利町役場は海の近く、小学校の隣にある。川本、東と合流し、待ち合わせの時間まで役場の駐車場で話をしていると、小学校の校庭から声がする。
「誰ー!?どこから来たんー?アメリカ!?(笑)」
元気な奈半利の子ども達だ。なんだか自分の子ども時代を思い出して懐かしくなりながら、待ち合わせに向かった。
今回、お話を伺うのは奈半利町役場の柏木雄太さん。ふるさと納税で奈半利町を押し上げた仕掛け人だ。

人口約3000人の町 奈半利。面積も文京区2つ分ほどの広さで、隣にある田野町など他の自治体との「境目」が(意識の上で)結構あいまい。住人の方のお仕事は主に、農家、漁師、JA、公務員(役場や学校など)。他は町外に通勤しているのだそう。
「町の活性化のためにはふるさと納税に賭けるしかない。」
ふるさと納税の制度が始まったとき、柏木さんはそう確信したそうだ。しかし、何といっても人口3000人の小さな町だ。地場産品といえるものは今までになかった。町の定食屋を回り何か売り出せるものがないかと探す、そんな日々から始まったという。
今までは「生計を立てるため」に作っていたものを、職業として魅力的なものにできないか。そんな想いだった。
そんな試行錯誤の中で生まれたのがゆず豚や米ヶ岡鶏といった畜産の奈半利ブランドだ。ゆず豚は60代のお父さんが、県外に行っている大学生の息子さんに「帰ってきてほしい」という一心で必死に考えた取り組みの結果なのだという。当初はこうしたキーパーソン2〜3件だけで始めたふるさと納税への取り組み、今では40億円に迫る規模に成長した。
奈半利町ではその寄付金を使って、返礼品を作る2つの工場を新設。高知県の取り組みで各自治体にある「集落活動センター」でもふるさと納税に関する作業に取り組んでいる。
「今までは作って終わりという意識だった。安い値で売るか、ご近所に配るか、自家消費するかだったものを、このふるさと納税をきっかけに変えていきたい。」
ふるさと納税の影
税収も増え、仕事も増えた。しかし、いいことばかりではない。ふるさと納税で「うまく」いったことによる弊害も大きい。
「ふるさと納税に依存している今は、悪い意味で勘違いしてしまっています」
税収2億円ほどの町に、40億円近くの税収が入ってくるまさに「ふるさと納税バブル」。どうしても奈半利町の抱える根本的な問題に正面から向き合えずにいる。
「結局ふるさと納税で、現状としては何も変わっていない。依存体質のまま。ここから抜け出さなくちゃいけないんです」
高知大の受田先生(セミが見た高知③)の言葉が浮かんだ。「さらなる刺激を求める」ってこういうことなんだな…。
ふるさと納税の返礼品が多くの住民が参画できる形になっているか。今は本来の市場とは違う「ふるさと納税市場」での戦い。まさに「ぬるま湯」の中での出来事なのだ。いつ崩れてもおかしくはない。
そして、ふるさと納税は今年度から制度が厳格化され、返礼品への制限も明確になる。
「奈半利への寄付は間違いなく減るでしょう。本物しか残らなくなる。ガクっと下がったときに本気になれるかどうか……今が勝負なんです」
「地域の若い人たちへ、雇用の受け皿を作りたい」その一心で進み続ける柏木さんと奈半利町。本当の勝負は今、始まったばかりだ。
人材不足!
奈半利町を含め、農業などの後継者のほとんどは、イベントなどで呼び込んだ結果、東京から来る人たちばかりだという。
柏木さんの口からしきりに出た言葉、それは「人材がいない/足りない」。
「カリスマ的なキーマンが欲しい。ある素材を見て、ビジネスにできるような人が」
ただでさえ、人口が少ないなかで、子どもは少なく、多くは町外に出て行ってしまう。町を変える人材が1人でも多くこの町に来てほしい。
人口3000人の町。1人の人間が背負う期待と責任は、東京では想像もできないくらい大きい。それは重荷でもある。ただ、「代わりのいる自分」ではなく、1人の人間を必要としてくれる地であることも確かだ。
若い力、外からの力が1人でも増えれば、「分かってもらえないことも多い」という柏木さんのような人たちももっとやりやすくなるのになあ。
地方創生の罠
そして、胸に刺さった言葉がある。
「でも、街が応援してくれないとできない人ならそもそもうまくいかないんです」
地方は東京より「劣って」いる、だから補助金や支援を受けて、東京に負けない環境にして、それから……
「地方創生」というと、無意識のうちにそんな意識でいなかったか。補助金がもらえるなら……そんな姿勢では遠くない将来に破綻してしまうだけだ。
東京にない、今は誰も注目していない「宝石」を見つける。これこそが地方の生きる道なんじゃないのか。「東京>地方」の前提で「腫れ物に触る」態度が「地方創生」なのだとしたら、そんなものは上手くいかない。「かわいそうな」地方を助けたい。そんな想いなのならやめておいた方がいいと思った。ふるさと納税の町 奈半利での滞在を通して気付かされた。当たり前のようでいて気付かなかった「地方創生」の罠だ。
本音
賛否両論のふるさと納税について、柏木さんは最後にこう漏らした。
「ふるさと納税が都会に不利って言われるけど….戦後から今までずっと、教育するだけ教育して、人材を輩出してきた地方にこれくらいあってもいいんじゃないかって思うよ……」
東大生には都会育ちの人たちが多い。そんな皆にこそ分かってほしい。僕も三重県伊勢市で生まれ育ったから痛いほど分かる。どんどん人が出ていく地方。若い人が日に日に出ていく。この「寂しさ」を。元気がなくなっていく気持ちを。「ああ…昔は元気だったのに…」そんな声を。そんな中で、その地で生きる人たちは懸命に「今」を生きている。
星ってこんなにきれいだっけ
そして、お隣田野町の宿泊先へ。柏木さんのご厚意に甘えて車で送っていただいた。
実は、田野町にあるゲストハウスに3人で予約していたのだが、手違いで泊められないというハプニングが。すると宿のお母さんが自宅に泊めてくださるという。
今から向かうと電話を入れると、
「近くのスーパーでうどん買っておいで」
何かな?と思っていると、なんと軍鶏の鍋をごちそうになってしまった!!人生初の軍鶏だったが、これがもうなんと表現していいのか分からないほどにおいしい!

温かい、そしてユーモアあふれる最高のお母さんだった!
そして、夜に外に出ると街灯の明かりもほとんどない。あたりは真っ暗だ。空を見上げると、思わずため息が出てしまった。
東京に出てきて2年。忘れていた。夜空の星ってこんなにきれいだったっけ。
朝は軍鶏の鳴き声で目覚めた。さあ、今日も長い一日の始まりだ。

文・写真 矢口太一(孫正義育英財団 正財団生・工学部機械工学科3年)
Mail: taichikansei@gmail.com (記事へのご意見大募集中!)
【セミが見た高知 シリーズ】