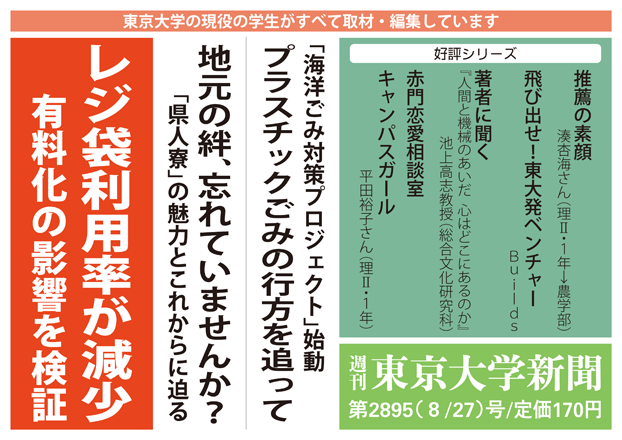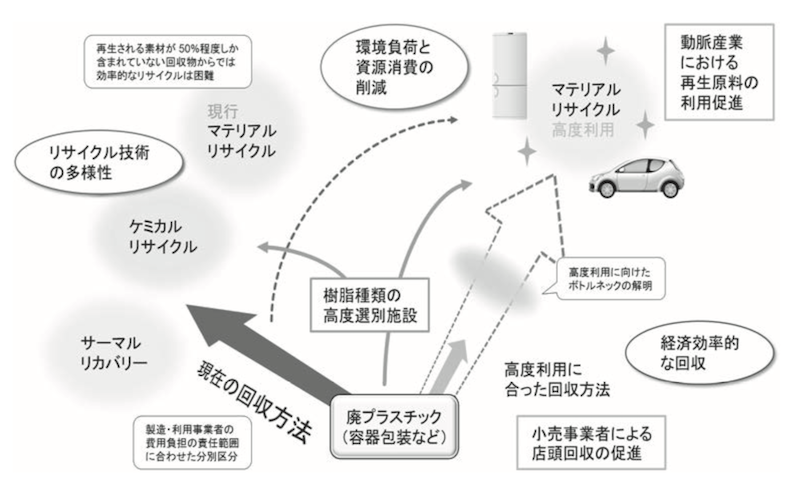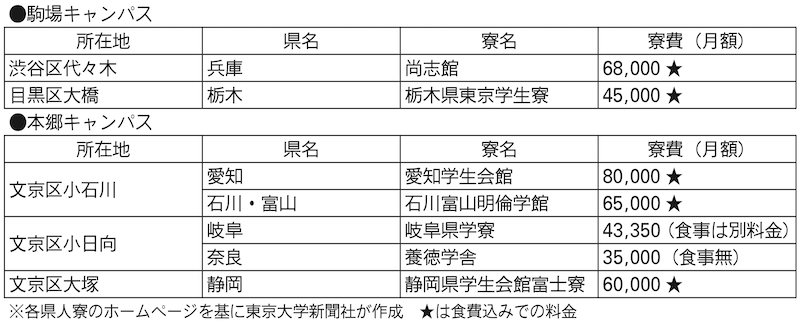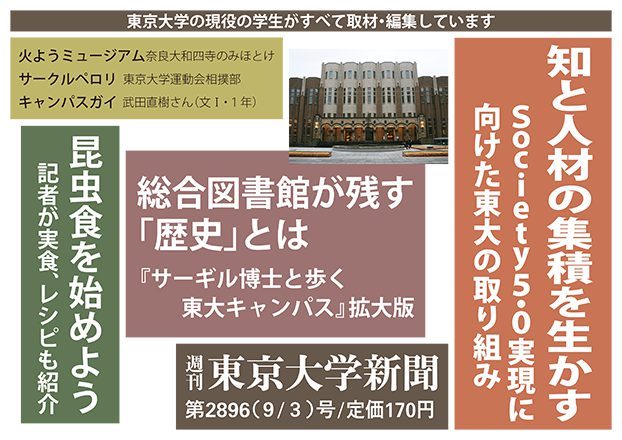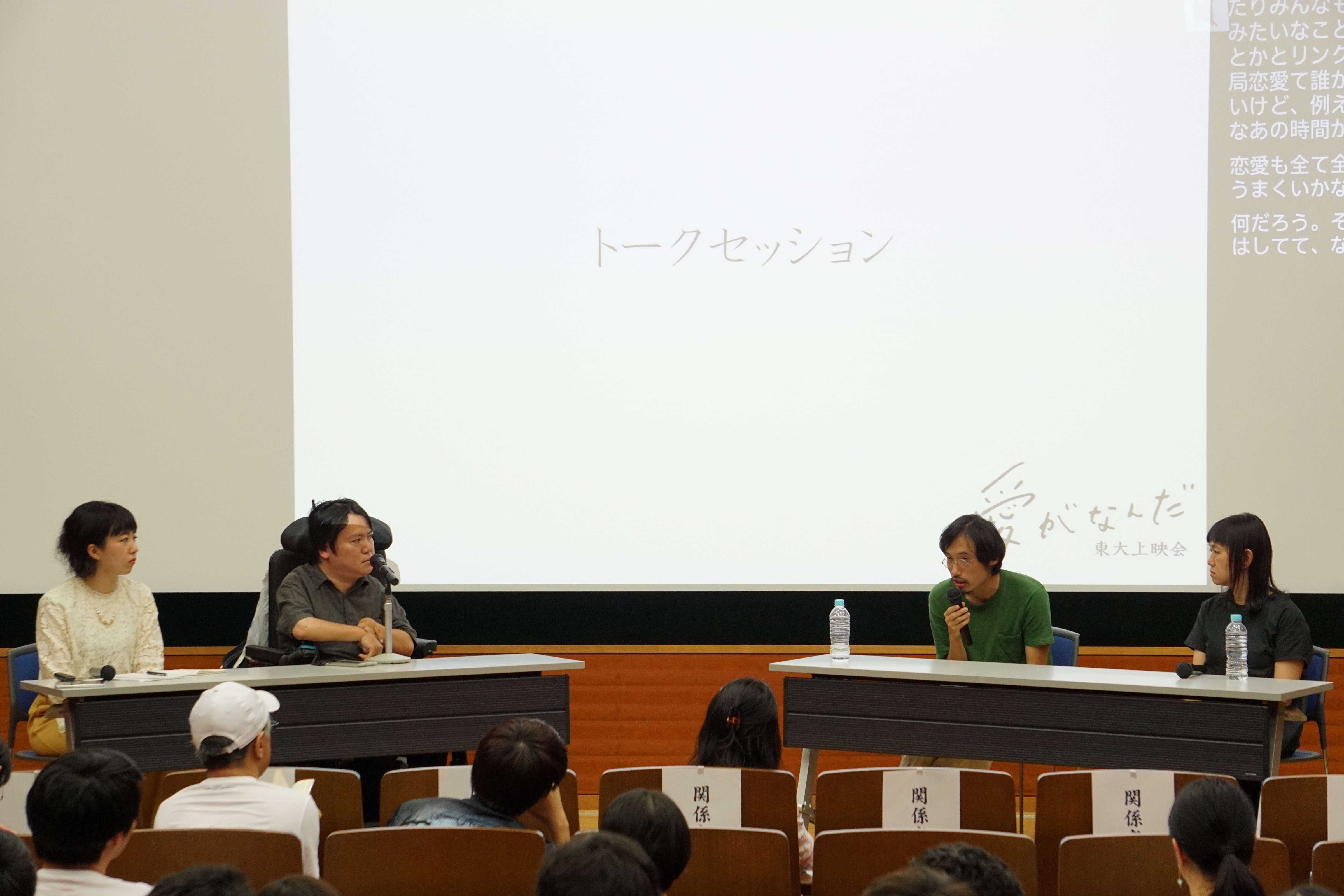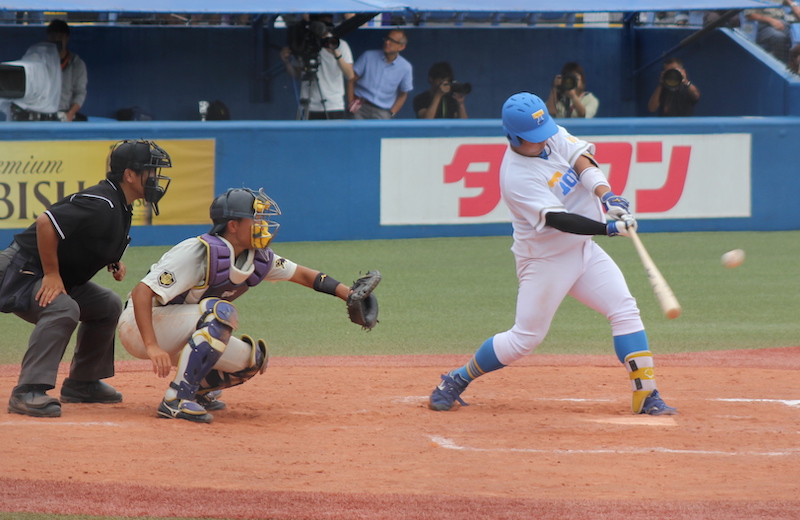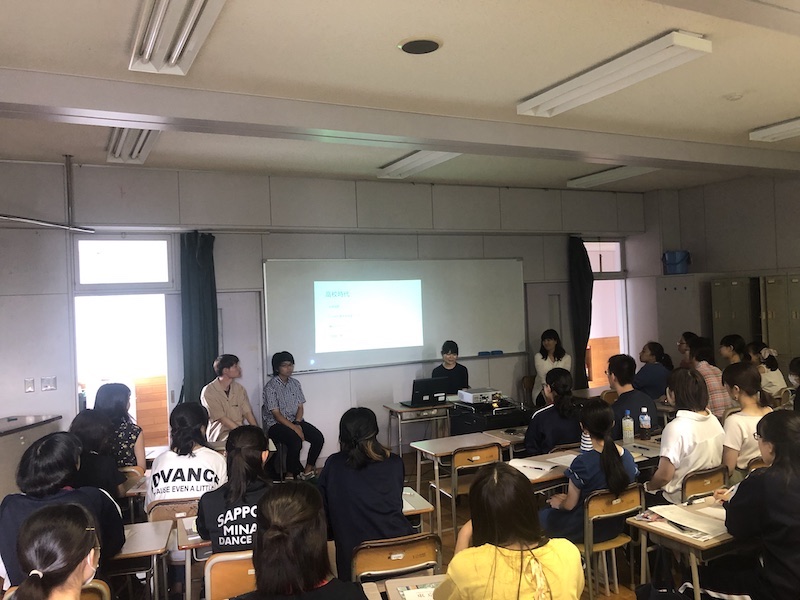昨年国内最大級のピアノコンクールであるピティナピアノコンペティション特級にて、東京藝術大学などトップの音楽大学の学生を差し置いて優勝するという快挙を成し遂げたピアニストの角野隼斗さん。情報理工学系研究科に在籍し、フランス音響音楽研究所 (IRCAM) で機械学習を用いた自動採譜の研究に従事するなど、工学研究者としての顔も併せ持つ。音楽と研究を両立させる角野さんの話からは、東大入学後の多様な可能性を垣間見ることができるだろう。記事後半では、牛田智大氏など多くの著名な若手ピアニストを輩出し、角野さんを幼少期から支えてきたピアノ指導者の金子勝子さんにもインタビューを行い、ピアニストになるために必要なことや、音楽大学に行かずに音楽をすることについて聞いた。
(取材・円光門 撮影・円光門、宮路栞)
角野隼斗(すみの・はやと)さん(ピアニスト) 2018年工学部卒業。現在、情報理工学系研究科修士2年。幼少期から国内外のピアノコンクールに入賞し、18年ピティナピアノコンペティション特級グランプリ、及び文部科学大臣賞、スタインウェイ賞受賞。多くのリサイタルを展開し、これまでに国立ブラショフ・フィルハーモニー交響楽団、日本フィルハーモニー交響楽団オーケストラと共演。
――子供の時から数々のピアノコンクールで優勝してきた角野さんですが、演奏技術を維持、発展させていくため には毎日の継続的な練習が必要です。ピアノと勉強はどのように両立させてきたのでしょうか
両立しているという意識はありませんでした。音楽と算数の両方に興味を示していたのを親が上手に僕の好奇心の向く方向に導いてくれたのも大きかったと思います。小5の夏から塾に入った経緯もその延長線上で、いつしか受験勉強に専念していました。中高時代はバンドで編曲活動をしたりドラムを叩いていてピアノは毎日1時間くらいの練習でしたね。むしろ本格的にピアノに取り組んだのは大学に入ってからでした。
――そうは言っても、中3の時にはショパン国際コンクール in Asiaで金賞を受賞しています
もちろん、コンクール前には集中して何時間も練習しました。しかしなによりも、幼少期の聴音や和声感覚、小学校の時に固めた技術的な基礎が有利に働いたのだと思います。師匠の金子勝子先生が開発した「指セット」という練習法で、5本の指を独立させそれぞれの実力の差をなくすことを、まだ小さい時から叩き込まれました。
――音楽大学ではなく東大を選んだ理由は
一つは、両親の助言です。進路を迷っているならまず東大に入ってから本当にやりたい事を見つけていくのがベストでは? と、東大押しでしたね(笑)。実際僕自身も、中高時代ピアノをそこまで真剣にやっていたわけではないので、音楽大学で一日中ピアノと向き合う勇気は当時の僕にはありませんでした。あと、音楽大学には派閥同士の争いとかがあって、そこから離れて自由に音楽をしたいというのもあったと思いますし、プロになるかどうかはさておき東大に行っても音楽はできると思ったんですよね。
――音大生をうらやましいと思うことはありますか
今でも音大コンプレックスはありますよ。音大生しかいない所にいると何となく肩身が狭いような気がするし,彼らは演奏はもちろん音楽理論や音楽史を包括的に学ぶので、楽曲に対して深い理解を持っていて、自分の不勉強さを恥じることはあります。
――しかし、2018年には東京藝術大学などトップの音大生を差し置いて、ピティナピアノコンペティション特級でグランプリを受賞しました
はい、そのおかげで、音楽関係の色々な人たちに出会うことができましたし、共演やリサイタルのお話も多くいただきました。また、フランスの世界的なピアニストであるジャン=マルク・ルイサダの友人の作曲家が演奏を聴きに来てくれて、それがきっかけで後日フランスでルイサダのレッスンを受けることができました。
――東大に入ってよかったことは
東京大学ピアノの会に入ったら、クラシック音楽に情熱を注ぐ人たちに多く出会って、刺激を受けました。あと、東大POMPというサークルで引き続きバンド活動をしたのですが、こういう経験って音楽大学では得られなかったと思いますね。金子先生にも、「あなたは音大生よりも楽しんでピアノを弾いてるね」って言われます。
――現在は演奏活動の傍ら、情報理工学系研究科に修士2年として在籍していますが、どのような研究をしていますか
主に機械学習を用いた自動採譜の研究をしています。まず、音源データをMIDIデータという抽象化・記号化された情報に変換します。採譜はMIDIデータを楽譜に還元することでなされるわけですが、正確な採譜がなされるためには、音源データとMIDIデータの差をできるだけ縮めなければいけません。そこで、MIDI データを再生した際の音源データと、元の音源データを比べて、データ変換時のパラメーターをどう調節すれば両者の差は縮まるのかということを、人工知能に学習させています。
――研究の意義は何だと考えますか
まず、聞いたものを楽譜にするシステムを構築することには一定の需要があると思います。また、メガバイト単位の音源データをキロバイト単位のピアノロールに還元できれば、それだけ情報量の濃度が高くなるわけです。音楽面に関しては、楽譜では半音までしか表記できなかった音の差が、ピアノロールではもっと細かく表記できるようになります。ピアノロールの表記を元に演奏、作曲すれば、いずれ音楽が12平均律の枠組みから脱却して新たな次元に到達するのではないかと考えます。
――研究のアイデアが演奏に生きることは
ありますね。私は自動採譜だけでなく自動編曲の研究も行っているのですが、オーケストラをピアノに編曲する時に、弦楽器のレガートを、打鍵したら音が減衰していくピアノでどう表すかという問題があります。弦楽器のダイナミクスをピアノで近似するには、ピアノで一音が出されてから減衰するまでの時間を考えて、つなげれば良いということが分かりました。このようにして、音源データの細かいダイナミクスに着目することで演奏のヒントを得ることがあります。
©︎平舘平
――昨年 9 月からは半年間、フランス音響音楽研究所 (IRCAM)に留学されました
私が所属している原田研究室は機械学習の研究を行っているところなのですが、音に特化しているわけではないので、教授からフランスで自分の専門を深めてみればどうかというお話をいただきました。フランスでは演奏家や作曲家といった実践者と工学研究者などの理論家の協同作業を見ることができて、とても刺激的でした。日本の音楽界では実践は音楽大学、理論は一般大学とくっきり分かれていますが、不思議に思いますね。分かれずに一体となっている方が、双方にとって面白いのではないでしょうか。
――たしかに、日本では実践者を目指すならば音大に行く傾向が強いですね。イェール大学など海外の総合大学では、学内に音楽学部があって、演奏家や作曲家の養成が行われています
あいにく高校生の時はそのような学部の存在を知りませんでした。知っていたら進学していたかもしれません。
――研究の最終的な目標は
音楽の本質は音そのものだろうか、それとも音を創り出している人間なのだろうか、という問いを突き詰めたいです。ぼくは前者だと思うんです。会話相手が人間ではなく機械であることを見破れるかというチューリングテストと同じように、演奏が機械によるものか、人間によるものかというテストをして、区別できなければ音楽の本質はただ音の構造だということになるじゃないですか。楽曲を純粋な記号としてモデル化することで人間的なものを全て排した時、音楽にどのような表現が生まれてくるのかということに関心があります。
――今後の展望は
修士号を取得後はベンチャー系の企業に就職して、そこで音に関する研究プロジェクトに参加させてもらいながら、ピアニストとしての演奏活動もする、というのが目下の計画です。ゆくゆくは、人工知能等の技術を自らの音楽活動に活かしたいですね。
◇
金子勝子(かねこ・かつこ)さん(ピアノ指導者) 国立音楽大学ピアノ科卒業。昭和音楽大学・大学院ピアノ科教授などを経て、現在社団法人PTNA(全日本ピアノ指導者協会)理事・運営委員・指導法研究委員会委員長。
――はじめに、先生が開発した練習メソッド「指セット」について教えてください
単に指をよく回らせるための教材は世間にたくさんあります。でも5 本の指は付き方が一本一本違う上に、実力の差があるわけで、その状態のままだと何回も弾けば弾くほど実力の差が出てきて下手になってしまうのです。この問題を解決する教材が今までなかったので、各指の実力差を縮める「指セット」というメソッドを私が作りました。もっとも、角野くんは生まれながら良い指をしていたので、「指セット」をそれほどやる必要はなかったのですが。
――角野さんはどのような生徒でしたか
昔からピアノ一筋というよりは、音楽全般が好きという子でしたね。中学に入学した時、親御さんから「この子は勉強の道の方が合っていると思うので、ピアノはそこそこにお願いします」って言われたんです(笑)。本人もクラシック音楽以外に編曲や即興、ロックバンドなんかやったりして、興味の幅が本当に広かったですね。昨年ピティナピアノコンペティション特級で優勝したのを見て初めて、彼はピアニストになれる、と思いました。
――東大や東大院に入ってから、角野さんの演奏が変わったと思うことはありますか
より考えてから音を出すようになりました。中高生の時は、何も考えずにぱらぱらと弾いていることがありました。そんな時、左手のこれは何を意味しているか、フレーズの中でこのハーモニーはどの方向性を帯びているのかなどと聞くと、角野くんの答えは私が考えていたことに、いつもぴたりと合っていました。音楽は彼の中に内蔵されているのだけど、出し方が分からなかったわけですね。今でも、よく聞くと左手で出す音が平坦になっていたり、レガートにもう少し内容がほしいと指摘することはたまにありますが、ハーモニーの方向性や連続音の差異などの表現の仕方をよく考えて弾いていると思います。大学院で研究する上で、音楽ってこういうことなんだなということが分かってきたのでしょう。
――先生のもう1人の著名な門下生である牛田智大さんと、角野さんの共通点はありますか
2人に共通するのは、音大のような環境とは縁がないということと、頭が良いということですね。牛田くんは義務教育の期間までしか学校に通わなかったですが、中学校の時はすでに音楽事務所のジャパン・アーツに所属してプロとして演奏活動を行っていましたから、1週間の内3日間だけ勉強して、それでもクラスで5番以内に入っていたそうです。なにせ2時間ものプログラムを演奏時に全部頭に入れなければいけないですから、ピアニストになるには頭が良くなければいけません。
――逆に2人の違いは
本人がピアニストになろうと意識した時期は違いました。牛田くんは小学校3年の時からでしたが、角野くんは昨年ピティナで優勝してからですね。
――角野さんは、今でも音大コンプレックスがあると言っていますが
音大コンプレックスなんて感じる必要はないですよ。確かに音大には切磋琢磨できる環境が備わっているという点では良いですが、ピアニストになるに当たって何より重要なのは本人の資質と努力、そして環境です。今回も江口玲先生(東京藝術大学准教授、ジュリアード音楽院ピアノ科出身。ニューヨークと東京を行き来しながら作曲活動を行う)の目にとまり、角野くんは共演させていただきました。角野くんは資質という点では天才的なものがあり、楽曲に対する理解の速さや、リズム感、音色感、バランス感覚、暗譜力、音楽的な頭の良さを持ち、そして中高時代にドラムをたたいていたためかリズム感も抜群です。私は大学教員を引退した後時間的な余裕が生まれたので、角野くんのような優秀な門下生により力を注ぐことができました。現在リサイタルも多く持っている彼には週1回2~3時間のレッスンをしています。時々外来の名教授のレッスンなどを入れることも大切だと思います。
――音大に行かなくても、良いピアニストになる環境は整えられるということですか
もちろん、王道は音大に進学することですが、諸事情でその道を選ばなかった、選べなかった人の道が必ずしも閉ざされるわけではないということです。
――角野さんは、人間による演奏と区別のつかない機械による演奏が可能になるのではと考えていますが、先生はどう思いますか
私は不可能だと思いますね。芸術というのは、人間が創り出すものですから。作曲家と演奏者の人生が演奏に反映されているからこそ、音楽は美しい芸術となるわけです。角野くんの研究が今後どうなるかは、楽しみに待っていることにしましょう(笑)。
※この記事は現在発売中の『現役東大生がつくる東大受験本 東大2020 考えろ東大』 に掲載されたインタビュー記事を加筆修正したものです。他にも受験生でない方にとっても面白い情報満載の書籍ですので、ぜひ合わせてご覧ください。