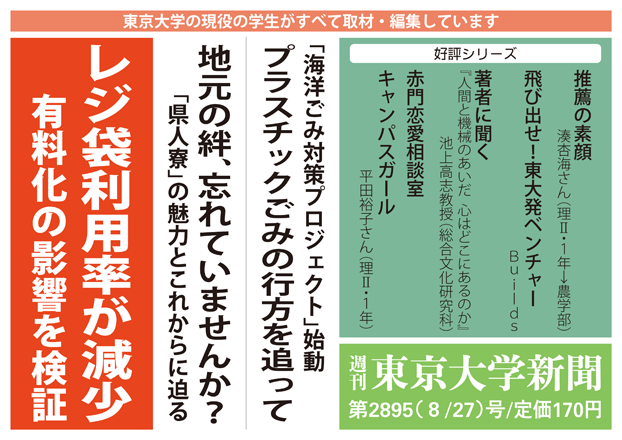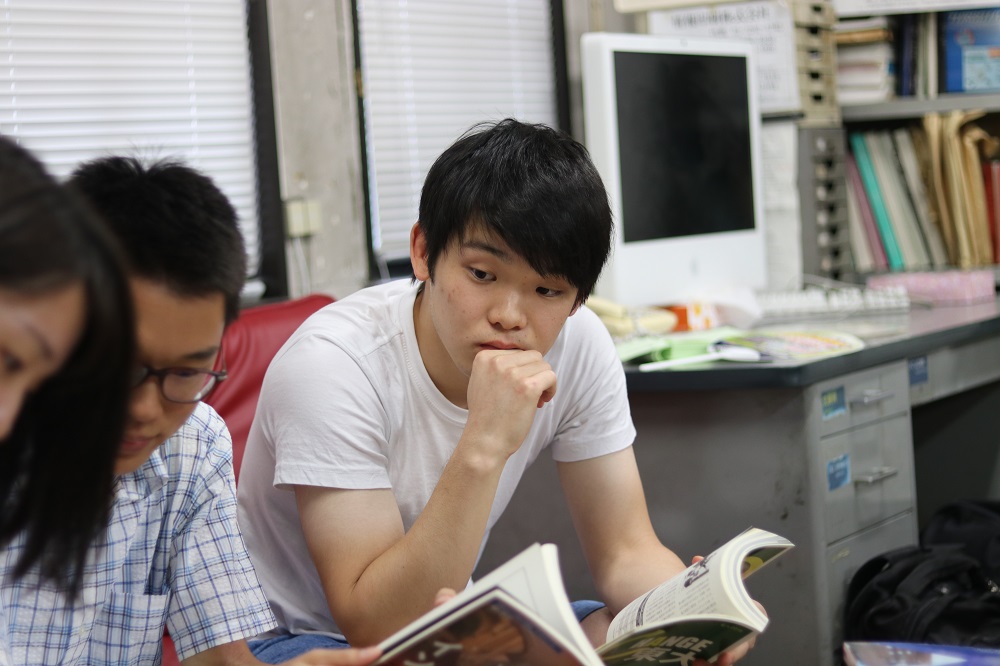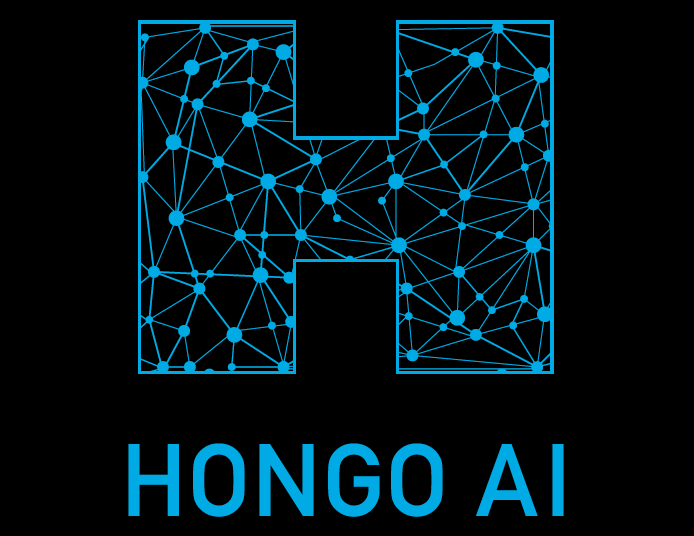地方から東大へ導く一冊
東大受験本『東大20XX』シリーズの最新版『東大2020』が発売された。本書は受験勉強から学生生活、卒業後の進路まで東大のあらゆる情報を発信し、特に受験情報が手に入りにくい地方高校生の手助けとなることを目的の一つとしている。本シリーズを受験生時代に読んでいた地方出身の3人が、その魅力を語ってくれた。
(取材・田中美帆、長廣美乃 撮影・円光門)
![]()
気合い注入にも、息抜きにも
━━まずは自己紹介をお願いします
畠山さん
文学部人文学科フランス語フランス文学専修課程4年生で入学時は文Ⅱです。出身は宮城県の私立中高一貫校聖ウルスラ学院英智高校で、東大進学者はほとんどいませんでした。
![]()
畠山茉理絵(はたけやま・まりえ)さん。
松藤さん
工学部電気電子工学科3年生です。入学時は理Ⅰ。福岡県の県立修猷館高校出身で、毎年10人程度が東大に進学します。
![]()
松藤圭亮(まつふじ・けいすけ)さん。
矢口さん
工学部機械工学科3年生です。推薦で工学部に合格し理Ⅰに入学しました。出身校である三重県立伊勢高校の東大進学者は年2人程度です。
![]()
矢口太一さん(やぐち・たいち)さん。
記者
私も本シリーズを読んでいまし た。文Ⅲの2年生です。出身は神奈川県の私立中高一貫校フェリス女学院高校で東大進学者は年5~10人です。
━━本シリーズを知った経緯は
畠山さん
高2の夏に東大のオープンキャンパスに参加し、東大新聞のテント販売で見掛けました。
記者
赤門近くのテントですね。
畠山さん
そうです。
松藤さん
自分は家族での東京旅行の際、東大を訪れてみることになり、書籍部でこの本を見つけました。
矢口さん
父が地元の書店で買ってきてくれました。受験関連コーナーに置いてあったようです。
記者
オープンキャンパスで、高3の時です。実は東大新聞に入ろうと思ったのもこの時がきっかけです。
━━東大受験を意識し始めたのはいつごろですか。またそのきっかけは
畠山さん
高1の冬です。それで翌年のオープンキャンパスに参加してみました。
松藤さん
本シリーズを買った中2時点では考えていませんでした。意識し始めたのは高3の4月ごろです。シリーズがきっかけの一つになったと思います。
矢口さん
小1の時に漠然と「日本一だから気合い注入にも、息抜きにも東大に行く!」と思っていました。情報がないからこそそういう考えになったのでしょう。父もそれを知っていてこの本を買ってきてくれたんです。
記者
高2ごろだと思います。とりあえず高い目標を持とうと。
━━東大に入る前と後でイメージのギ ャップはありましたか
矢口さん
「みんな普通の人間じゃん」と思いました。アホなところもあるなと。
畠山さん
分かります。変わった人しかいな いと思っていました。実際は普通に良い人が多くないですか?
矢口さん・松藤さん
そうですね。
松藤さん
自分はだいたいイメージ通りでした。一つ残念だったのは、『東大2012』の表紙の図書館が改装中で入れなかったこと(笑)。
━━本シリーズはどの程度読んでいましたか。どういった時に読んでいたか も教えてください
畠山さん
一通り読みました。受験勉強への気合いを入れたい時は「教員からのメ ッセージ」を読んでモチベーションを上げ、勉強法で悩んだら「勉強法アドバイス」を参考にしました。
松藤さん
「穴が開くほど読んだ」と言いたいくらいですが実際に穴は開いていません(笑)。『東大2012』の巻頭インタビューからは「科学者って格好いい」と大きな影響を受け、理系に進みたいと思うきっかけにも。初めは受験勉強のことは分かりませんでしたが学年が上がると中身をじっくり読むようになりました。
矢口さん
主にサークル紹介や家賃などの生活に関わることを、雑誌のように息抜きで読んでいました。
━━一番役に立った企画は何ですか
畠山さん
やはり「合格体験記」ですね。どの時期に何を勉強すれば良いのか、どのくらい点数を取らなければならないのかなどを参考にしました。周りに教えてくれる人もいなかったので。複雑な進学振分け制度(当時)についても見ました。
松藤さん
「不合格体験記」を最も読みました。面白くて役に立つ企画だと思います。「科類紹介」も、例えば理Ⅰ〜Ⅲの違いといった基本的なところが分からなかったため参考にしました。
矢口さん
「地方からの東大受験」を熟読し受験の流れをつかみました。「合格体験記」は賢そうで「参考にならへんな」 と思いながらも、受験のイメージがぼんやりと湧きました。卒業後のことが書いてあるのも良かったです。
信用度高い記事 ネットにはない
━━好きだった企画や印象に残った企画はありますか
畠山さん
「教員からのメッセージ」です。入試問題を教員が作っているのは分かっていたのですが、実際に顔や名前が見えると実感が湧きます。「不合格体験記」も面白かったです。
松藤さん
これを書いている人たちも最終的に受かったんだというのが救いです。
畠山さん
「判定なんて覆せ!」という言葉に安心した記憶があります。
記者
「不合格体験記」が人気ですね。私は浪人していたのでこの記事を活用しました。
松藤さん
それは僕も印象に残りました。「教員からのメッセージ」も、こんな先生方に会いたいと思いましたし、入学後に実際に会うこともできました。巻頭インタビューも毎年力を入れてい ると思いますが、東大出身の格好いい大人が特集されていて「自分もこんなふうになれるかも」と刺激になりました。推薦入試が始まった翌年の推薦入学者へのインタビューでは、合格した人に感心した記憶があります。
矢口さん
僕は逆に「自分も行けるのでは」 と推薦入試の受験を検討するきっかけになりました。また1人暮らしやアルバイトなどの生活面に関する企画が印象的でした。ミス東大・ミスター東大の企画も見て華やかじゃん!と思いました。
━━本シリーズの魅力はどのようなところだと思いますか
畠山さん
インターネットに載っていない情報があることです。東大教員に入試について聞くなんて東大生しかできないですよね。また、取材された人の顔と名前が出ているのはブログなどと違い信頼度が高いです。実際にこういう人がいて、こういう経路をたどって合格したんだなと見えるのが良い。
松藤さん
僕も名前が書いてあることで信用できました。東大のあらゆる情報が1冊にまとまっているところも良い。入学前から入学後の生活、卒業後の進路など時系列でまとまっていますよね。
記者
私は今年の『東大2020』で「大学院生の生活紹介」と「就活体験記」 を担当しました。まだ大学にすら入っていない読者に向けて大学院の情報は気が早いかなと思っていましたが、大学に入って終わりではなく卒業後のことを考えるきっかけになるのは良いですよね。
矢口さん
僕にとってはこの本が唯一自分と東大がつながる糸でした。周りは田んぼだし学校には東大の「と」の字もない中で、東大での生活を意識できたことは大きいです。受験のことが書いてあるだけの本だったなら自分にはあまり響かなかったかな。
━━首都圏と地方の東大受験生の情報格差を埋めることが本シリーズのコンセプトの一つとなっていますが、その点に関してはいかがですか
畠山さん
地方には格差を意識することもないほど情報がないと思います。私も初めは何も知らず、基本的なことはこのシリーズで知りました。しっかり情報を集めた方が良いと思いました。
松藤さん
この本自体が地方で認知されにくいです。福岡の大きい書店には僕が見た時は2冊あった程度。この本の存在を浸透させることがまず必要だと思います。
矢口さん
情報格差を感じたことは多くあります。自分の親戚の中で大学に行った人がほとんどいないため、そもそも大学受験とは何か、大学に行くとは何かという状態でした。意思を固めてしまえばいくらでも情報は探せるので、そんな環境下で東大受験への意思を固める一つの補助としてこのシリーズは役に立ちました。
畠山さん
そういうのが一番大事ですよね。
矢口さん
周りと逆行しないと僕らは東大には来られないので、逆向きに走るきっかけの一つとして。
━━東大受験に関する他の情報源には どんなものがありましたか
畠山さん
やはりインターネットですね。
矢口さん
同じく。予備校のウェブサイトや個人の体験記などを見て参考書を選ぶ参考にしました。東大に入学した先輩たちの講演を聞いたり直々に連絡を取ったりもしていました。
松藤さん
自分も先輩から話を聞きました。受験勉強より東大での生活の方が気になっていました。インターネットでもUmeetや東大新聞オンラインなど東大の学生団体から情報が発信されていますよね。Twitterのコミュニティーも意外と情報源になります。数学を勉強している人たちのコミュニティーがあって、その中にいた何人かの東大生たちの話から東大生活を垣間見ていました。あとは学校の図書館にあった東大新聞を読んでいました。
記者
どんな記事を読んでいましたか。
松藤さん
全部です。実は高校生の時に新聞部に所属していたので。大学の先生に会いに行く東大新聞の企画を真似して九州大学の教授にお話を聞きに行ったことも。
地方でも貪欲に情報収集を
━━本シリーズに要望はありますか
畠山さん
先ほど松藤さんも言っていたように、もっと多くの地方受験生の手に入るようになれば良いと思います。私の地元の書店にもありませんでした。
松藤さん
一つ目は同じく販路拡大。存在を知らない人も多いので。二つ目は情報量を減らしてほしくないということ。実は図書館で1990年代のものからこのシリーズを全て読んだんです。
記者
すごい。ありがとうございます!
松藤さん
そこで、文字数が徐々に減り写真や漫画が増えていることに気付きました。読みやすくて時代の流れには合っているのですが。なくなった企画もありますよね。「学部学科ガイド」は、情報自体はインターネットで見られるのですが、まとまっているという魅力があったので寂しいです。
矢口さん
確かにまとまっていた方が分かりやすい。
松藤さん
巻頭インタビューももっと分厚くても……。
矢口さん
「合格体験記」は格好付けたい人が多いと思うんです。でもそれだと、地方の人からすると完璧な人が合格するんだなというメッセージしか入ってこない。実際に会うとゲームばかりしていた人や、趣味や恋、部活に没頭していた人もいる。でもここには書かれていないですよね。都会の進学校の人だと、あいつも東大を受けるけど適度に遊んでるし、自分も大丈夫だろうなどと思えるかもしれませんが、近くにそういうモデルがいないければ無駄に焦ってしまいます。完璧じゃないと受からないのでは、と。奨学金のことも地方だと知りたい人は多いでしょう。
松藤さん
確かに「これだけ奨学金が出る」 などと親を説得するのに使える本だと良いですね。
矢口さん
お金や性別の問題で諦める女性も周りにたくさんいました。そういう人たちを一人でも救えたら。
松藤さん
そういう意味ではいろいろな属性の人が登場するとうれしいですね。
畠山さん
出身地や高校が公立か私立かなどはよく気にして見ていました。
松藤さん
ほぼ自分と同じ属性の人に親近感が湧いたり。
矢口さん
浪人に関する企画も欲しいです。宅浪していた人の情報とか。高3の弟に本シリーズを買ってあげたのですが、不合格だったときに浪人するか、金銭的な問題で悩んでいます。
畠山さん
そういえば、このシリーズに情報格差を埋めるというコンセプトがあることは初めて知りました。
矢口さん
確かに。
松藤さん
そういうメッセージをもっと強く出してもいいのでは。
畠山さん
あと留学に関する情報もあるとうれしいです。交換留学や奨学金の制度を知らず、お金持ちしか行けないのかと思っていました。
松藤さん
東大を受ける人は皆買う可能性がある本なのだからマーケティングすべきですよ。せっかくデザインも東大らしくない、堅くなくて手に取りやすいものに変わったんですから。
━━地方高校生にメッセージを
畠山さん
情報格差があるのは仕方がなく、与えられた環境で頑張るしかない。でも、情報を求め続けることはできます。貪欲に情報を集め続ける姿勢が大切だと思います。
松藤さん
僕は一言で。『東大2020』を買いましょう!
矢口さん
それで終わるのがいい気がしますが……。大学に入るまでの受験勉強は正直、生まれた場所や親に左右される部分が大きいです。しかし大学に入ってからは、商売でも研究でも自分で求めれば何でもできます。頑張った分だけ価値があるとこの2年間でたくさん思いました。いわゆる都会のお坊ちゃんやお嬢さんに追い付き追い抜くことができる。「悔しかったら何年かかろうが来いよ」と言いたい。まずは『東大2020』を買おう!
(社告)
※『現役東大生がつくる東大受験本 東大2020 考えろ東大』は好評発売中です。受験以外にも東大情報満載の書籍ですので、ぜひ併せてご覧ください。
『本書はやみくもに東大受験を勧めるものではありません。高校生の皆さんに少しでも東大について考える契機にしてもらい、その上で大学受験に立ち向かってもらうこと、東大が未来の東大生を迎える上でどんな問題があるのか考えてもらうことを目標に制作しました。本書が読者の皆さんの「考える」に貢献することを願っています。』
(東大2020編集長 宮路栞 巻頭言より)
![]()